実績じゃなくても戦える。「どう向き合ったか」が伝わる濃厚ストーリー
目次
- ▶︎実例①:継続力×泥くささ(野球部)
- ▶︎実例②:裏方視点での貢献力(サッカー部)
- ▶︎実例③:組織再建のリーダーシップ(バスケ部)
- ▶︎実例④:フィジカル班の仕組み化(ラグビー部)
- ▶︎実例⑤:初心者育成での貢献(ソフトテニス部)
- ▶︎実例⑥:けが期間の支援力(ラクロス部)
- ▶︎実例⑦:人との信頼構築(野球部)
- ▶︎実例⑧:分析と提案力(バレーボール部)
- ▶︎実例⑨:世代間連携の推進(陸上部)
- ▶︎実例⑩:地域貢献と継続(柔道部)
実例①:継続力×泥くささ(野球部)
「私は大学4年間、硬式野球部でプレーヤーとして一度も公式戦に出場することはありませんでした。それでも“チームの勝利に貢献したい”という思いから、毎朝6時からの自主練、夜練の後のノート振り返りを欠かさず継続しました。練習後にはピッチャー陣の球種データを自分で記録して分析し、月1回のミーティングで共有。最終学年には副主将としてベンチ内の戦術担当を任され、“この人ならチーム全体を底上げしてくれる”という評価を得ました。どんな状況でも前向きに工夫を重ねる継続力は、自分の最大の強みです。」
実例②:裏方視点での貢献力(サッカー部)
「チームでは戦力としての出場機会は多くありませんでしたが、“自分にしかできない貢献を探す”という視点で行動しました。主に映像分析を担当し、ディフェンスラインの連携ミスや相手チームの攻撃パターンをフレーム別にまとめたレポートを作成。それをベースにした戦術変更により、3試合連続無失点という結果につながりました。自分が直接得点するわけではなくても、全体の改善に繋がる視点を持って動けることを誇りに思っています。」
実例③:組織再建のリーダーシップ(バスケ部)
「3年時に主将を任された際、部員の練習参加者が週3名以下、部内の会話もほぼゼロという状況でした。まず“チームの目的”を再定義し、『卒業までに“信頼されるチーム”になる』という目標を掲げて、週1回のミーティングを開始。出席したメンバーに応じてメニューを柔軟に組み、練習後には個別フィードバックを加えることで定着率を上げていきました。半年後には平均出席者が20人を超え、卒業時には3年ぶりの大会出場を果たしました。空気を整え、土台から立て直す力に自信があります。」
実例④:フィジカル班の仕組み化(ラグビー部)
「私はフィジカル班のリーダーとして、“感覚的だった筋力トレーニング”を見える化するプロジェクトを立ち上げました。選手10名を対象に月ごとの体重推移・筋トレ回数・食事内容をスプレッドシートで一括管理し、個別の目標設定と達成支援を行いました。半年後には8名が目標値をクリアし、3名が公式戦先発メンバー入り。継続できる仕組みをつくることで、個人の成長とチーム力を底上げできるという感覚をつかみました。」
実例⑤:初心者育成での貢献(ソフトテニス部)
「新歓担当として、初心者が安心して継続できる環境づくりに注力しました。体験練習では“できる喜び”を感じられるラリー設計を工夫し、1on1の育成ペア制度を導入。先輩と新入生が固定ペアになり、技術とメンタル面をフォローする体制をつくった結果、初心者の継続率が前年の2倍に向上。“教える側・教わる側が互いに育つ”という仕組みづくりの面白さを強く感じました。」
実例⑥:けが期間の支援力(ラクロス部)
「私は2年時のけがで半年間プレーヤーとして活動できなかった期間、“自分がチームに何をできるか”を徹底的に考え、選手のフィードバック記録や動画素材の編集、遠征の調整業務に力を入れました。選手が見落としがちなポイントを可視化し、練習改善に繋げたことで、現場での信頼を獲得。復帰後も“裏方の視点を持てるプレーヤー”として起用されました。役割に縛られず、自分の価値を見つける柔軟さはどんな現場でも活きると考えています。」
実例⑦:人との信頼構築(野球部)
「私は試合に出場できない状況でも、ベンチ内での声かけ・指示出し・観察を徹底し、“場を動かす存在”になることにこだわりました。技術以上に、“周囲から信頼される行動”を積み重ねることで、チームに深く関われることを実感しました。」
実例⑧:分析と提案力(バレーボール部)
「スコアラーとしてプレー記録を取り続ける中で、“なぜ失点が続くのか?”という疑問から、守備ゾーン別の成功率を算出。それをもとにした“守備シフトの提案”が春季大会で採用され、実際にブロック成功率が12%向上しました。数字を“意味のある情報”に変える視点を鍛えることができ、今後もこうした分析力を業務改善にも活かしたいと考えています。」
実例⑨:世代間連携の推進(陸上部)
「陸上部では“長距離と短距離の部員同士がほとんど交流しない”という分断課題があり、私は“合同練習月間”と“クロスカテゴリー座談会”を企画しました。トレーニング効率や食事管理の知見が共有され、互いの競技理解が深まった結果、合同合宿実施へとつながりました。チーム内に“異なる視点を橋渡しする”企画力と対話力を養えたと思っています。」
実例⑩:地域貢献と継続(柔道部)
「地域の柔道教室で、小学生への技術指導を4年間継続して行いました。ただ教えるだけでなく、“教室終了後の振り返りレポート”を作成し、来週への改善点や一人ひとりの変化を記録。その積み重ねにより、保護者からの信頼も高まり、“中学生クラスを新設してほしい”という相談もいただくように。誰かの成長に継続的に関わることが、自分にとって最もやりがいのある仕事だと感じています。」

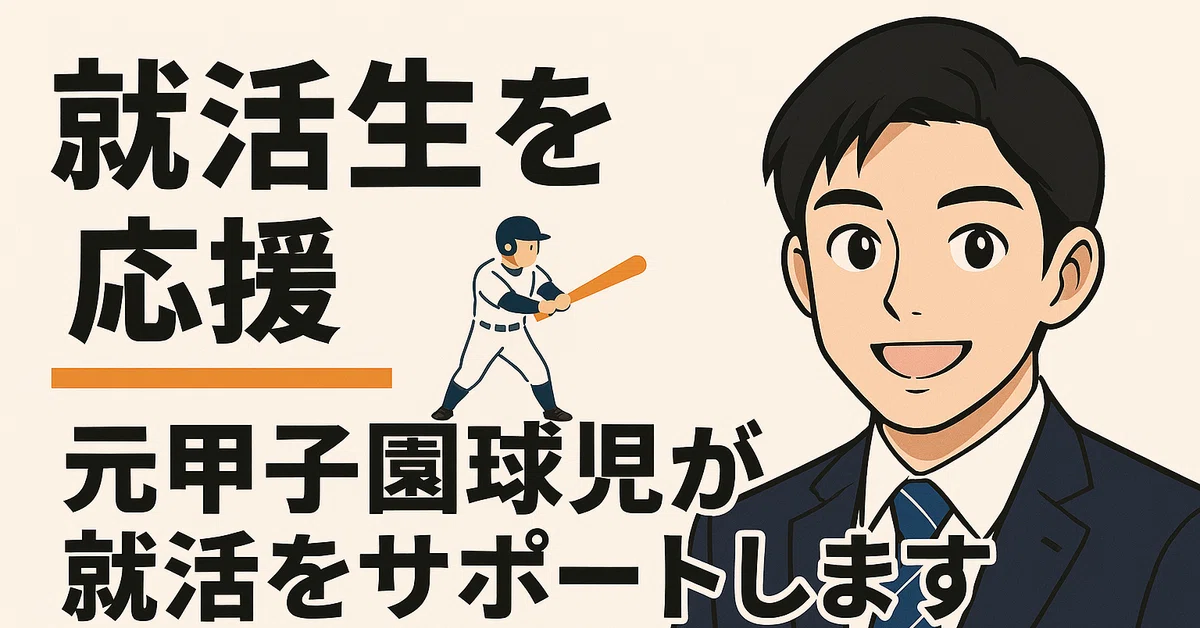


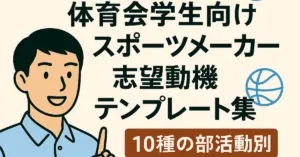
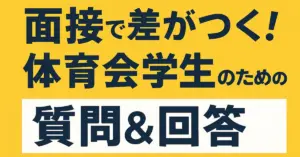

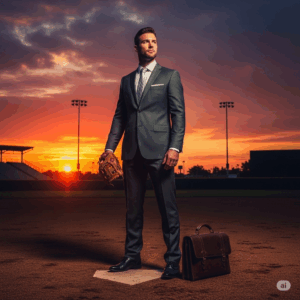
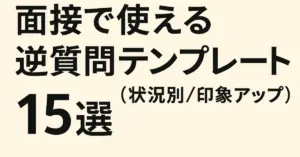

コメント