はじめに
はじめに、自己PRと聞くと、何をどう書けばいいのか悩んでしまいますよね。
特に体育会学生の皆さんは、部活動で培ってきた強みや経験をどうアピールすればいいのか、
わからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな体育会学生の皆さんに向けて、
自己PRの書き方から、すぐに使える例文までを10選紹介します。
自分の言葉であなたの魅力を最大限に伝えられる自己PRを作成しましょう!
Q.自己PRってなに?
自己PRとは、簡単に言うと「自分の強みや長所をアピールすること」です。
採用担当者は、自己PRを通して
「あなたがどんな強みを持っていて、会社でどう活躍してくれるか」を知りたいと考えています。
そのため、あなたの経験やスキルをただ伝えるだけでなく、
その経験から何を学び、その結果、入社後にどう活かせるのかまでを具体的に伝えることが重要です。
学歴フィルター 偏差値45の大学 就活で逆転するために必要なこと
就職・転職 職種 解説|自分に合う仕事を見つける完全ガイド – 体育会系の就活&ライフサポート
自己PRの基本構成
説得力のある自己PRを作成するためには、
以下の3つのステップで構成を組み立てることがおすすめです。
- 結論: まず、あなたの強みを一言で伝えましょう。
- 根拠: 強みを裏付ける具体的なエピソード(部活動の経験など)を説明します。
- 貢献: その強みや経験を、入社後にどう活かせるかをアピールします。
【自己PR 例文10選】体育会学生の強みをアピールする
1. 継続力
「継続力」 は、日々の厳しい練習を乗り越えてきた体育会学生の最大の武器の一つです。
目標に向かってコツコツと努力を続けられる力をアピールしましょう。
例文
私の強みは、目標達成に向けた継続力です。高校から続けているサッカーでは、レギュラーになることを目標に、毎日欠かさず自主練習に取り組みました。特にシュートの精度を上げるため、練習後にはグラウンドに残り、1日100本のシュート練習を3年間継続しました。最初はなかなか成果が出ませんでしたが、地道な努力を続けた結果、3年生の時にはレギュラーの座を勝ち取ることができました。
この経験から、大きな目標も日々の小さな努力の積み重ねで達成できることを学びました。貴社に入社後も、この継続力を活かし、地道な業務にも真摯に取り組み、長期的な目標達成に貢献したいと考えております。
2. 協調性・チームワーク
「協調性」 は、チームスポーツにおいて不可欠な能力です。
チームメイトと協力し、一つの目標に向かって努力した経験をアピールしましょう。
例文
私の強みは、目標達成のために周囲を巻き込む協調性です。大学のバスケットボール部では、チームが連敗続きで士気が下がっていた時期がありました。私は副キャプテンとして、チーム全体の状況を把握し、選手一人ひとりと話し合いを重ねました。その中で、各メンバーが抱える課題や不満を共有し、チーム全体で解決策を模索する機会を設けました。具体的には、練習メニューに全員で意見を出し合ったり、ミーティングの時間を増やしたりしました。
この取り組みの結果、チームの一体感が増し、次第に勝利を重ねられるようになりました。この経験から、私はチームで働くことの重要性と、周囲を巻き込みながら目標を達成する力を培いました。貴社に入社後も、チームメンバーと協力しながら、プロジェクトを成功に導くために貢献したいです。
3. リーダーシップ
キャプテンや副キャプテンを務めた経験がある人は、「リーダーシップ」 をアピールできます。
チームをまとめ、その結果、目標達成に導いた経験を具体的に伝えましょう。
例文
私の強みは、目標達成に向けてチームを牽引するリーダーシップです。大学の野球部ではキャプテンを務め、チームを全国大会出場に導くという目標を掲げました。チームには個々の能力が高い選手が揃っていましたが、まとまりがなく、連携が課題でした。私は、個々の能力を最大限に引き出すために、選手一人ひとりの得意なプレーや役割を明確にしました。また、定期的に選手と1対1で面談を行い、個人の目標とチームの目標をすり合わせることで、モチベーションの向上に努めました。
その結果、チームは一丸となり、目標だった全国大会出場を果たすことができました。この経験から、私はチームをまとめ、目標達成に向けて導く力を身につけました。貴社でも、このリーダーシップを活かし、チームのパフォーマンス向上に貢献したいです。
4. 課題発見・解決能力
練習や試合の中で課題を見つけ、
その課題を解決するために試行錯誤した経験は、「課題発見・解決能力」 のアピールにつながります。
例文
私の強みは、課題発見・解決能力です。大学のバレーボール部では、チームのレシーブ力不足が課題でした。私はこの課題を解決するため、チームメイトと協力して、他校の試合動画を分析したり、コーチにアドバイスを求めたりしました。その結果、レシーブのフォーメーションに問題があることが分かりました。私は、ポジションごとに最適な動きを考案し、練習メニューに組み込みました。
この取り組みの結果、チームのレシーブ力は格段に向上し、失点を大幅に減らすことができました。この経験から、私は課題を論理的に分析し、具体的な解決策を実行する力を身につけました。貴社でも、この能力を活かし、業務上の課題を積極的に解決していきたいです。
5. 向上心・探求心
常に上を目指し、自分のスキルを磨いてきた経験は、「向上心」 や 「探求心」 としてアピールできます。
例文
私の強みは、常に学び続ける向上心です。大学の陸上競技部では、長距離走のタイムを短縮するために、様々なトレーニング方法を研究しました。コーチの指導に加えて、自分で専門書を読んだり、プロ選手の動画を見てフォームを研究したりしました。また、栄養学の知識も学び、日々の食事にも気を配りました。
その結果、目標としていた大会で自己ベストを大幅に更新することができました。この経験から、私は目標達成のために自ら学び、知識を深めていくことの重要性を学びました。貴社に入社後も、この向上心を活かし、新しい知識やスキルを積極的に習得し、自己成長を続けたいです。
6. 規律性・責任感
厳しい規律の中で活動し、
自分の役割を全うしてきた経験は、「規律性」 や 「責任感」 のアピールになります。
例文
私の強みは、組織の一員としての規律性と責任感です。大学の硬式テニス部では、チームの勝利のため、自分の役割を常に意識して行動しました。たとえ個人的な調子が悪くても、チームの士気を下げないよう、常にポジティブな言動を心がけました。また、練習の準備や後片付けも、他のメンバーの手本となるように率先して行いました。
その結果、チームメイトからは「〇〇さんがいるから頑張れる」と言われるようになりました。この経験から、私は組織の一員として、自分の役割を全うし、周囲に良い影響を与えることの重要性を学びました。貴社でも、組織の一員として規律を遵守し、与えられた業務に責任を持って取り組みます。
7. プレッシャーへの強さ・精神力
試合の勝敗がかかった場面や、
厳しい練習に耐えてきた経験は、「プレッシャーへの強さ」 や 「精神力」 のアピールに繋がります。
例文
私の強みは、どのような状況でも冷静に判断できる精神力です。大学のラグビー部では、試合終盤の逆転をかけた場面で、冷静に状況を判断し、最適なプレーを選択する役割を担っていました。相手チームの猛攻にさらされる中でも、チームメイトを落ち着かせ、正確なパスを出すことに集中しました。
この経験から、私はプレッシャーのかかる状況でも、焦らずに自分のやるべきことに集中できる力を身につけました。貴社に入社後も、厳しい状況や予期せぬトラブルに直面した際にも、冷静に状況を判断し、最善の行動をとることで、チームや会社の目標達成に貢献したいです。
8. ストイックさ
自分の限界に挑戦し、
常に高みを目指してきたストイックさは、自己成長への意欲としてアピールできます。
例文
私の強みは、目標達成に向けて自分を律するストイックさです。大学の水泳部では、日本学生選手権の出場を目標に掲げ、厳しいトレーニングを自分に課しました。練習メニュー以外にも、毎日の睡眠時間や食事内容を記録し、常に体調管理を徹底しました。また、練習の成果を分析するために、自ら動画を撮影してフォームを細かくチェックしました。
このストイックな取り組みの結果、目標としていた日本学生選手権に出場することができました。この経験から、私は目標達成のためには、自分自身に厳しく向き合うことの重要性を学びました。貴社でも、このストイックさを活かし、日々の業務に真摯に取り組み、プロフェッショナルとして成長し続けたいです。
9. 計画性・目標達成能力
試合の勝ち方や練習メニューを考え、
計画的に取り組んできた経験は、「計画性」 や 「目標達成能力」 のアピールに繋がります。
例文
私の強みは、目標達成に向けた計画性です。高校のバドミントン部では、地区大会で優勝することを目標に掲げました。私は、優勝までの道のりを具体的にイメージし、長期的な計画を立てました。まず、自分とチームの課題を洗い出し、それぞれの課題を克服するための練習メニューを作成しました。練習の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を修正しました。
この計画的な取り組みの結果、目標通りに地区大会で優勝することができました。この経験から、私は目標を達成するためには、現状を分析し、具体的な計画を立てて実行することの重要性を学びました。貴社に入社後も、この計画性を活かし、業務を効率的に進め、目標達成に貢献したいです。
10. 瞬発力・判断力
試合中のとっさの判断や、急な状況変化に対応する力は、
たとえば、ビジネスシーンでも役立つ 「瞬発力」 や 「判断力」 としてアピールできます。
例文
私の強みは、状況を瞬時に判断し、最善の行動をとる瞬発力です。大学の柔道部では、相手の動きを瞬時に見極め、最適な技を繰り出すことが求められます。試合中、相手のわずかな隙を見逃さずに、一瞬で技をかけることを常に意識して練習に励みました。
この経験から、私は刻一刻と変化する状況に対応する判断力と、迅速に行動する瞬発力を身につけました。貴社に入社後も、この能力を活かし、変化の速いビジネス環境において、迅速かつ的確な判断を下すことで、会社の成長に貢献したいです。
実績じゃなくても戦える。「どう向き合ったか」が伝わる濃厚ストーリー
▼実例①:継続力×泥くささ(野球部)
私は大学4年間、硬式野球部でプレーヤーとして一度も公式戦に出場することはありませんでした。それでも“チームの勝利に貢献したい”という思いから、毎朝6時からの自主練、夜練の後のノート振り返りを欠かさず継続しました。練習後にはピッチャー陣の球種データを自分で記録して分析し、月1回のミーティングで共有。最終学年には副主将としてベンチ内の戦術担当を任され、“この人ならチーム全体を底上げしてくれる”という評価を得ました。どんな状況でも前向きに工夫を重ねる継続力は、自分の最大の強みです。
▽実例②:裏方視点での貢献力(サッカー部)
「チームでは戦力としての出場機会は多くありませんでしたが、“自分にしかできない貢献を探す”という視点で行動しました。主に映像分析を担当し、ディフェンスラインの連携ミスや相手チームの攻撃パターンをフレーム別にまとめたレポートを作成。それをベースにした戦術変更により、3試合連続無失点という結果につながりました。自分が直接得点するわけではなくても、全体の改善に繋がる視点を持って動けることを誇りに思っています。」
▼実例③:組織再建のリーダーシップ(バスケ部)
「3年時に主将を任された際、部員の練習参加者が週3名以下、部内の会話もほぼゼロという状況でした。まず“チームの目的”を再定義し、『卒業までに“信頼されるチーム”になる』という目標を掲げて、週1回のミーティングを開始。出席したメンバーに応じてメニューを柔軟に組み、練習後には個別フィードバックを加えることで定着率を上げていきました。半年後には平均出席者が20人を超え、卒業時には3年ぶりの大会出場を果たしました。空気を整え、土台から立て直す力に自信があります。」
▽実例④:フィジカル班の仕組み化(ラグビー部)
「私はフィジカル班のリーダーとして、“感覚的だった筋力トレーニング”を見える化するプロジェクトを立ち上げました。選手10名を対象に月ごとの体重推移・筋トレ回数・食事内容をスプレッドシートで一括管理し、個別の目標設定と達成支援を行いました。半年後には8名が目標値をクリアし、3名が公式戦先発メンバー入り。継続できる仕組みをつくることで、個人の成長とチーム力を底上げできるという感覚をつかみました。」
▼実例⑤:初心者育成での貢献(ソフトテニス部)
「新歓担当として、初心者が安心して継続できる環境づくりに注力しました。体験練習では“できる喜び”を感じられるラリー設計を工夫し、1on1の育成ペア制度を導入。先輩と新入生が固定ペアになり、技術とメンタル面をフォローする体制をつくった結果、初心者の継続率が前年の2倍に向上。“教える側・教わる側が互いに育つ”という仕組みづくりの面白さを強く感じました。」
▽実例⑥:けが期間の支援力(ラクロス部)
「私は2年時のけがで半年間プレーヤーとして活動できなかった期間、“自分がチームに何をできるか”を徹底的に考え、選手のフィードバック記録や動画素材の編集、遠征の調整業務に力を入れました。選手が見落としがちなポイントを可視化し、練習改善に繋げたことで、現場での信頼を獲得。復帰後も“裏方の視点を持てるプレーヤー”として起用されました。役割に縛られず、自分の価値を見つける柔軟さはどんな現場でも活きると考えています。」
▼実例⑦:人との信頼構築(野球部)
「私は試合に出場できない状況でも、ベンチ内での声かけ・指示出し・観察を徹底し、“場を動かす存在”になることにこだわりました。技術以上に、“周囲から信頼される行動”を積み重ねることで、チームに深く関われることを実感しました。」
▽実例⑧:分析と提案力(バレーボール部)
「スコアラーとしてプレー記録を取り続ける中で、“なぜ失点が続くのか?”という疑問から、守備ゾーン別の成功率を算出。それをもとにした“守備シフトの提案”が春季大会で採用され、実際にブロック成功率が12%向上しました。数字を“意味のある情報”に変える視点を鍛えることができ、今後もこうした分析力を業務改善にも活かしたいと考えています。」
▼実例⑨:世代間連携の推進(陸上部)
「陸上部では“長距離と短距離の部員同士がほとんど交流しない”という分断課題があり、私は“合同練習月間”と“クロスカテゴリー座談会”を企画しました。トレーニング効率や食事管理の知見が共有され、互いの競技理解が深まった結果、合同合宿実施へとつながりました。チーム内に“異なる視点を橋渡しする”企画力と対話力を養えたと思っています。」
実例⑩:地域貢献と継続(柔道部)
「地域の柔道教室で、小学生への技術指導を4年間継続して行いました。ただ教えるだけでなく、“教室終了後の振り返りレポート”を作成し、来週への改善点や一人ひとりの変化を記録。その積み重ねにより、保護者からの信頼も高まり、“中学生クラスを新設してほしい”という相談もいただくように。誰かの成長に継続的に関わることが、自分にとって最もやりがいのある仕事だと感じています。」
まとめ
いかがでしたか?
体育会学生が持つ強みは、部活動で培ってきた経験の中に隠されています。
今回紹介した例文を参考に、あなたの経験を具体的なエピソードとともに伝えることで、
あなたの魅力を最大限にアピールすることができます。
ぜひ、自分の言葉でオリジナルの自己PRを作成し、就職活動を成功させましょう!
🌸新生活、何から始める?|学生・転職者向け「暮らしの不安」を解消する7つの便利サービス【実体験レビュー付き】 – 就職、転職活動をサポート!多彩なテンプレを用意

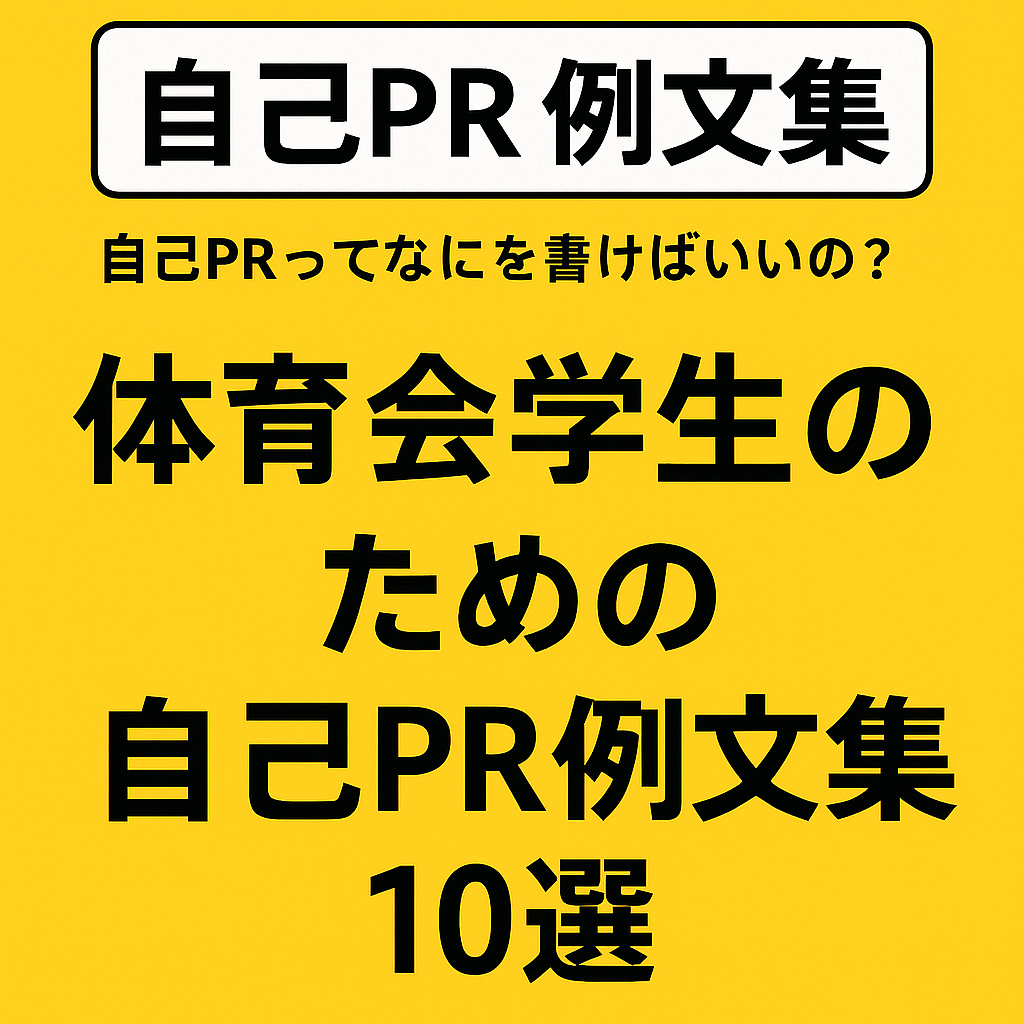
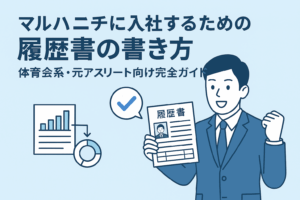




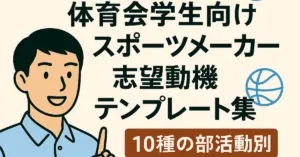
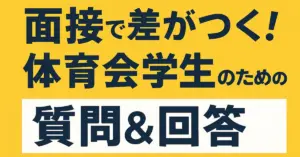
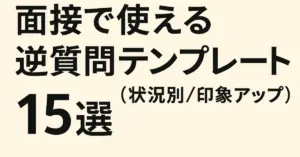
コメント